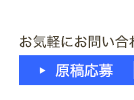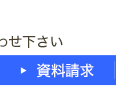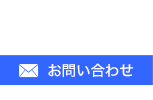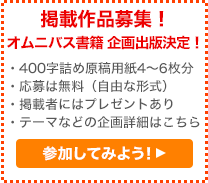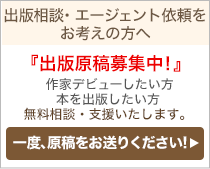スタッフ・インタビュー

A文学会- We read the works for authors
A文学会は、大々的に広告をうつわけでもなく、ホームページを見渡しても刊行した本のタイトルや表紙画像などは一つもない。
いまどきそんな出版社のホームページも珍しい。だが、新規での出版希望の原稿応募者は減るどころか、増え続けている。これもまた珍しい。
あなたの原稿への付加価値だけを探求した出版プロデューサーたち。インタビューを通じて、彼らの内面そのものに触れてみました。
もし、あなたにプロの作家と同じように専属の出版プロデューサーがついていて、毎回書き上げた原稿を読んでくれたら……。毎日書くことが楽しくて、心から元気になれる。そしてどんどん原稿のクオリティが上がる……。書き上げた原稿はあなたにとって、それほど大切なものだと思います。
私たちA文学会が、あなたの原稿を読むことが出来るのは、ほんの数回に過ぎません。だからこそ、あなたが書き上げた原稿を、あなた自身が読み直し、推敲することの楽しさや素晴らしさを感じていただくことが、大切だと考えます。 私たちの存在価値が、そこにあると思うからです。
1年経った時に、あなたの執筆スタイルや推敲の仕方、ひいては作品としての完成度の高さを実感していただくことができたら、当会で読ませていただいた時に得た満足が、より深く刻み込まれていくのだと思います。「また読んでもらおう」と思ってもらえるのだと思います。
そういった意味でも、当会への出版希望の原稿応募者のリピート率(なんと90%以上)は、私たちの誇りです。 作者の思い通り書かれた原稿をただ評価して出版を進めるサービスだけでは、やがて魅力は薄れてしまいます。なぜならば、その先の読者の感性はもっとしなやかでかつ厳しいものだからです。ですから誰もが原稿の付加価値を求めて「良いパートナーに巡り会いたい」と、流浪されているのだと思います。
添削技術の高さは当たり前のこと。それに加え、どこまで理解してもらえるか、どこまで共感し合えるかということを私たちは大切にしています。作者の原稿に対する悩みやこだわり、希望に対して、互いの共感が深いほど、私たちにとっても全ての経験や技術を活かす場所が明確になっていきます。 あらたに執筆を学ぶ喜びや厳しさをともに分かち合いながら、人の心に伝わる作品を創ってほしいと私たちは考えております。
そして、この「厳しい文芸の世界」に、一人でも多くの真の作家と呼べる才能を送り出すことを願っております。
あなたの原稿を通して、お互いが高め合える存在になること。
あなたが作家への階段を一歩登ることで、お互いが同志になること。
そして、あなたの出版のためのエージェントになること。

編集後記
ただ出版とか編集という、ありふれたフレーズが似合わない。今までの出版界にはない、真の作家と呼べる才能を育て、世に送り出すことに真剣に向き合い、かつこの仕事が好きでたまらない人の、前進する力強さを感じずにはいられなかった。明るく出迎えてくれるスタッフと、華美な演出が全くない温かな空間。
日々、原稿を読む時間をたっぷり取っているのは、プライベートな感覚となにより、一人一人の書き上げた原稿に集中したいから。A文学会を創る時にスタッフが一番大切にしたことです。たとえ応募原稿が集中しても、このスタンスを崩さないのは「厳しく・丁寧」を心掛けるから。スタッフが語る丁寧は、約20年になる出版界での経験で積み重ねた引き出しをたっぷり使うことです。「今までの出版ノウハウや添削技術があっても、使い方が分らなければ仕方がない……」。さまざまな経験を自分の中でしっかりと消化して、次に活かす過程を積み重ねた人だから言える言葉。
ただ、スタッフはそんな理屈を心に置く人たちではありません。 海外在住の方が、帰国される際に原稿を届けてくれる。2時間かけて原稿を届けてくださる作者もいる。それらの事実は「ここにしかない満足」がある証だと思えます。
A文学会の作家養成・出版エージェントは、原稿を書いている全ての作者の期待を限りなく大きくさせます。期待している気持ちを満足させるのは、期待以上であることが必要です。 作家の世界、出版の世界は厳しい環境が当たり前の世界。スタッフがその中で培ったのは「書きたい、学びたい、出版した方を応援する(出版プロデュース)という仕事が好き」だという向上心。 出版界を陰で支え日々奮闘する中で、ここにいるスタッフが最終的に求めたのは、出会える全ての原稿に素直に向き合い、その作者のもっと自由で、もっと創造的な感性を探していくこと。それこそが、作者と作品に対する本当の優しさなのかも知れません。
A文学会はそんな組織です。どんな原稿でもより添い、その作者が喜んでくれることが嬉しい。そんな時間を永く過ごしてきた人が持つおおらかさを感じることができる唯一の出版社なのだと思います。
It’s based on a writer’s interview.